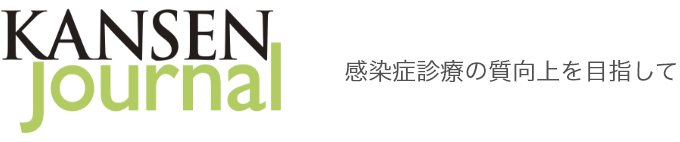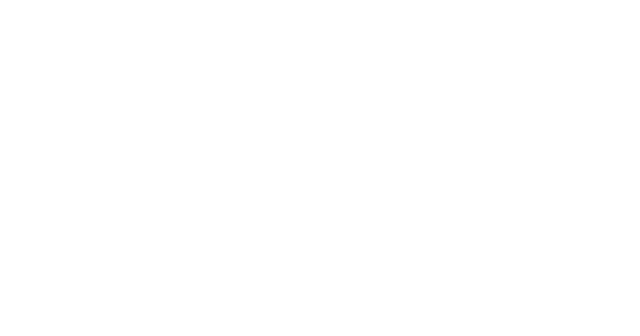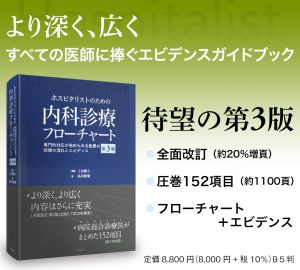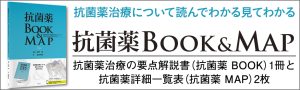「タイ・ミャンマー国境における現地で学ぶ熱帯感染症医師研修」の紹介
「タイ・ミャンマー国境における現地で学ぶ熱帯感染症医師研修」は、タイ王国のさまざまな地域・医療機関において、熱帯医学のみならず現地の医療体制、公衆衛生などについても直に学ぶことができる研修です。私も2015年度に参加させていただきましたが、大変有意義かつ楽しい2週間を送ることができました。
本研修は、国内では診療機会が少ない熱帯感染症の経験を、熱意ある若手医師に現地で積んでもらうことを目的として、大阪大学微生物病研究所(阪大微研)の先生方が中心となり2009年度から開始され、毎年継続されてきました。2020年度からはCOVID-19の世界的流行から開催中止となっていましたが、このたびKANSEN JOURNALの編集長でもある大阪大学感染症総合教育研究拠点(CiDER)の忽那賢志先生が新たに研修代表者となられ、阪大微研とCiDERの連携体制の下、この紹介文の作成時点では来年度から再開される見込みであるとのことです。
本研修は、例年7~8月(現地の雨季に当たる)に、タイ王国での約2週間の研修として開催されます。対象は熱帯医学および感染症診療を学ぼうとする意欲のある若手医師(目安として卒後3年以上、現地の医療従事者とコミュニケーションできる英語力を有していることが望ましい)で、募集人員は6名前後(予定)です。応募後の書類選考の結果、参加が決定された場合には、各種費用(旅費、宿泊費など)も大阪大学の規定に従って支給していただけます。
本研修の特長としては、タイ国内のさまざまな地域(タイ・ミャンマー国境の難民キャンプがある森林地帯に近いメソット 、東北部の中核都市であるコーンケンやウドーンターニー、インフラが整った大都市であるバンコクなど)の各医療施設において研修できる点が挙げられます(研修する地域・施設は変更の可能性あり)。メソットにあるミャンマーからの難民の診療を目的としたMae Tao Clinic、一方でコーンケンやバンコクにある大学病院・大規模病院といったように、患者背景や医療資源などが大きく異なる医療現場を訪れることができます。
実際の研修では、現地の医学生や医師と共に、デング熱、マラリア、メリオイドーシス、レプトスピラなどの診療を経験できます。内容としては病棟研修やプレゼンテーションを主としているものの、それら以外にも、エキスパートの先生方による講義や微生物検査室の見学(マラリアスメア実習なども含む)、肝吸虫の感染予防についての啓蒙活動の見学など、実に多彩な内容を経験できます。
また、最後に、熱意ある他の参加者の先生方と2週間にわたり時間を共有できることも本研修の大きな魅力の一つです。私自身、限られた時間の中で協力してチームでプレゼンテーションの準備をしたり、オフタイムを共に過ごしたりしたことは、今でも良い思い出になっていますし、研修終了後の今でも各先生方とはつながっており、いつも刺激を受けています。
以上、簡単ではありますが、「タイ・ミャンマー国境における現地で学ぶ熱帯感染症医師研修」の紹介をさせていただきました。興味を持たれた先生は、ホームページも参照いただき、ぜひご応募ください。